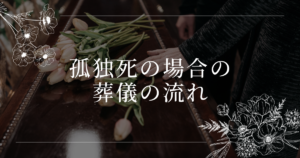ゴミ屋敷は高齢者に多い?原因と対策とは

家の中にゴミや物が積み上げられ、玄関や家の周りにまで溢れるような状態を、いわゆる「ゴミ屋敷」といいます。
ゴミ屋敷に住む人の多くは70代以上の高齢者だと言われています。
高齢者は体力や身体機能が低下していることから体への影響も大きく、ゴミ屋敷である状態が続くことでの病気やケガ、最悪の場合孤独死などに繋がる危険性があります。
今回は、高齢者の自宅がゴミ屋敷になってしまう原因とその対策についてご紹介します。
高齢者の自宅がゴミ屋敷になりやすい6つの原因

お盆や年末年始に実家に帰省した時に、ゴミ屋敷のようにあらゆる物が床に散らかっていて驚いたことのある人は少なくないようです。
掃除好きでいつもきれいに整理整頓していたご両親が急に片付けや掃除をしなくなるということは信じられないかもしれませんが、ゴミ屋敷は性格的な要因だけが関係しているわけではありません。
高齢者の自宅がゴミ屋敷となる原因は以下の6つが考えられます。
1.年齢による心身の衰え
病気によって体力や身体機能が低下する場合もありますが、ほとんどの人は加齢とともに心身が衰えることは避けられません。
心身が衰えることによって、片付けや、ゴミを分別して捨てるといった日常的な事がとても億劫に感じてしまい、ゴミ屋敷のきっかけとなってしまいます。
筋力だけではなく視力や聴力も衰えてしまうので、自然とやる気が落ちてくる高齢者も多いです。
年を取るとストレスに対しての耐性も衰えるため、ストレスによって体調を崩してしまうことも考えられます。
2.認知機能の低下
認知機能の低下は遺伝やストレス、精神状態や環境要因など様々な原因が関係しています。
脳梗塞やうつ病などの病気が原因であることもありますが、大きな要因とされているのは認知症です。
認知症を発症することで、理解力や判断力が低下してしまい、ゴミの日を忘れてしまったり、ゴミの分別ができなくなってしまいます。
また、認知症を発症すればもちろんのこと、認知症と診断されるレベルでなくても加齢により徐々に認知機能が低下してしまうため注意が必要です。
3.病気や精神疾患によるもの
高齢になると多くの人が持病を抱えているものです。
持病を抱えていることで身体的な衰えが進み、ごみ出しのような日常行為が難しくなります。
また、次のような精神疾患もゴミ屋敷になりやすいと言われています。
・うつ病
・ホーダー(ためこみ症)
・統合失調症
・ADHD
・アルコール依存症
これらは全て、本人には自覚しづらい病気です。
周囲の方が少しでも思いあたると感じたら、一緒に病院へ行って受診してもらうなど早めに対処するようにしましょう。
中でもホーダーは、精神疾患として認められたのが2013年と最近のことで、明確な治療法がまだない状態です。
ホーダー(ためこみ症)とは、物を過剰に集めることで喜びや安心感を得る一方で、不要な物であっても捨てることに不安や罪悪感、後悔といった苦痛を感じてしまう精神疾患のことです。
他人から見ると明らかにゴミに見える物やガラクタであっても、本人は囲まれていることで安心感を得ることができるため、どんなに不要なゴミでも捨てるという考えにならず、ゴミ屋敷が進行してしまいます。
4.もったいないという思い
ゴミ屋敷になってしまう高齢者の心理として、「物を捨ててはいけない」というものがあります。
若い世代とは比べ物にならないほど、もったいないという気持ちが強いので、不要な物でも「またいつか使うかもしれない」「置いておけば役に立つ」と思って必要以上に自宅にものをため込んでしまうのです。
しかし、「物を大切にすること」と「物を捨てないこと」は意味が違います。
収納スペースには限りがあるため、もったいない精神が行き過ぎてしまうとゴミ屋敷のようになってしまうこともあります。
5.セルフネグレクト
高齢者のゴミ屋敷が発生してしまう原因の一つとして、セルフネグレクトが考えられます。
セルフネグレクトとは、食事や着替えなど、本来であれば日常生活の中で行うべき行為をしない、あるいはできないため、心身の安全や健康状態を脅かす危険がある状態のことです。
若い人から高齢者まで年々増えている病気で、基本的な生活や服装にも気を配れず、他人へ助けを求めることもできなくなります。
当然、放置しておくと家がごみ屋敷になることが予想されますが、それだけでなく食事を取らない、必要な医療を受けないなど命の危険もあるため、注意が必要です。
6.周囲からの孤立
ごみ屋敷の原因として、若い人から高齢者まで多くの人に関係しているのが周囲からの孤立です。
ゴミ屋敷となっている家の住人は、約6割が一人暮らしだと言われており、すぐに周囲へ助けを求めることができない環境がごみ屋敷の大きな要因と言えるでしょう。
特に高齢者は、自分ができなくなったことを誰かに頼むと迷惑をかけるのではないかと考えてしまう傾向にあります。
家の中がゴミだらけになってしまうと、「誰にも知られたくない」という気持ちになり、ますます周囲から孤立したり、家族と疎遠になってしまうこともあるでしょう。
高齢者の自宅がゴミ屋敷となるリスク

高齢者のゴミ屋敷を手が付けられないといってそのまま放置するのは非常に危険です。
一般的によく言われている高齢者への影響は、次の4つです。
1.病気の発症、転倒によるケガの原因となる
洗っていない食べ物や飲み物の容器が部屋の中に散乱していれば、不衛生な環境となり、病気を引き起こしやすくなります。
また、転倒のリスクも高まり危険です。
高齢者は平坦な床面でもバランスを崩して転倒することも少なくありませんが、更に足元が大量のゴミに覆われていると、転倒のリスクは格段に高まります。
2.孤独死のリスクが高まる
ゴミ屋敷は面倒くさがりな人のように性格的な要因だけで作られるのではありません。
現代の日本では一人暮らしの高齢者が多く、隣近所のつながりが希薄になったことから、孤独死は誰の身にも起こり得る問題です。
ゴミ屋敷の問題は孤独死とも関連が深いため、ゴミ屋敷条例を制定している自治体もあります。
3.火災発生の危険性が高まる
埃がコンセントに被って引火し、火災が発生してしまうと、家の中のあらゆるゴミに火が燃え移って広がり、大火災に発展する可能性が極めて高く、非常に危険です。
また、住人が火災に気付いて逃げようとしても足元のゴミが邪魔になってしまい、逃げ遅れて亡くなってしまう可能性も高くなってしまいます。
4.近隣とのトラブルになりやすい
ゴミ屋敷は住居者本人だけの問題ではありません。
長期間放置されたゴミ屋敷からは異臭や害虫が発生し、被害が近隣住民にまで及びます。
結果的に近隣住民からクレームとなり、退去や行政代執行に発展してしまう可能性があります。
ゴミ屋敷にしないための対策

まず、家がゴミで溢れてしまう前に物を整理しておくことが重要です。
自分で整理整頓ができないようであれば、家族が定期的に自宅を訪れて片付けたり、費用はかかりますが、清掃業者に定期的に依頼することで家を清潔な状態に保つことができます。
親族や近隣住民との交流が少ない高齢者の場合は、こまめに訪問や連絡をしましょう。
片付けや掃除ができていないことや、冷蔵庫の中の食べ物が腐っているなどのことから、認知症などの病気に気付くきっかけにもなります
ゴミ屋敷の危険性を伝えることも大切です。
片付けなどの話をする時には、ゴミが溜まっていることを責めず、身体に危険があるということを伝えるようにしてください。
実際に溜まったものによる被害があった時や、病気が見つかった時など、状況に変化があったタイミングで話すと片付けを受け入れてもらいやすくなるでしょう。
ゴミ出しなどに困っている場合は、自治体のサービスを利用することもおすすめです。
高齢者のゴミ出しや安否確認のサービスを行っている自治体もあります。
認知症などの病気がある場合には、介護サービスの利用も検討しましょう。
まとめ
高齢者の自宅がゴミ屋敷になってしまう原因は様々ですが、高齢者にとってゴミ屋敷はリスクが非常に多く、早目の対処が求められます。
自分たちだけで問題を解決するのが難しい場合は、プロの専門業者や自治体に相談をすることもできます。
弊社でもゴミ屋敷の片づけを行っておりますので、ご相談ください。。
HOKYUでは生前整理・家財整理を承っております。
リサイクルをメインとし、ゴミを極力出さないことが特徴で、環境に優しい取組みを実施しております。海外輸出や老人介護福祉施設、児童施設への寄贈寄付なども行っております。
ぜひお気軽に何でもご相談ください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!